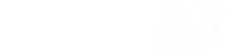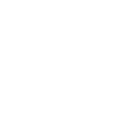沖縄の風俗業界で働く少女たちにスポットを当てたドキュメンタリー
3 views
<琉球大学の研究者が聞き取り調査をしてまとめた『裸足で逃げる』に記された、少女たちの仕事、家族、生い立ち、暴力と貧困のなかでの育児> 『裸足で逃げる――沖縄の夜の街の少女たち』(上間陽子著、太田出版)は、沖縄の複雑な環境下で暴力を受け、そこから逃れ、なんらかの"居場所"にたどり着いた女性たちの足跡を綴ったノンフィクション。 琉球大学教育学部研究科教授である沖縄出身の著者は、長らく非行少年少女の問題を研究してきた人物。1990年代後半から2014年にかけては東京で、それ以降は沖縄で未成年の少女たちの調査や支援に携わってきたのだという。本書は2012年の夏から2016年の夏にかけ、沖縄で行われた調査に基づいたものである。 取材に際しては各女性たちが指定する職場や馴染みの店などに出向いていき、ICレコーダーで録音しながら、子どものころの出来事、仕事のこと、家族やパートナーとの関係、子どもの育て方などを聞いている。 沖縄で、風俗業界で仕事をする女性たちの調査をはじめようと思ったのは二〇一一年だった。 沖縄の風俗業界には、未成年のときから働き出した女性たちがいると伝え聞いていた。年若くして夜の街に押し出された彼女たちがどのような家族のもとで育ち、どのように生活をしているかがわかれば、暴力の被害者になってしまう子どもたちの生活について話し、それを支援する方法について考えることができるのではないだろうか。(9ページ「まえがき」より) 取材対象となっているのは10代から20代の若い女性で、キャバクラで働いていたり、援助交際をしながら生活をしているという共通点がある。もともとは風俗業界で働く女性たちの仕事の熟達の過程、そして幼少時からの出来事に注目した聞き取り調査として行われたのだそうだ。 しかし、そこで聞いた話が予想していたよりもはるかに"しんどい"ものだったため、このような形になったというわけだ。事実、読んでみて痛感させられたのも、各人の環境の悪さだった。文字どおり「どうしようもできない」環境のなかで必死に自我を保とうとする女性たちの姿は、正直なところ痛々しくもある。 この調査でお会いしたシングルマザー全員が、自分のパートナーであり、子どもの父親でもある男性との関係を解消したあと、慰謝料も養育費も一銭ももらえず、単身で子どもを育てることを強いられていた。子どもを引き取った彼女たちは、スーパーやコンビニのレジの八〇〇円程度の時給よりも高い二〇〇〇円前後の時給のキャバクラで働くことで、子どもの面倒を見ることと生活費を得ることを両立させようとしていた。つまり、沖縄のキャバ嬢たちは、子どもをひとりで抱えて、時間をやりくりして生活する年若い「母」でもあった。(58ページより) 沖縄の風俗業界で働く女性について考えるとき、見逃すべきでないのはこの部分だろう。あくまで一般論の、しかも意地の悪い観点からすれば、風俗の仕事をすることは「自己責任」だ。どれだけ悲惨な目に遭おうとも、「その仕事を選んだのは自分でしょ」と考える人だっていないとは限らない。 しかし、こと沖縄に関していえば、そこまでドライにまとめることは難しそうなのである。その証拠に、ここに登場する女性たちはみな共通して、「困難からなんとかして逃れよう」という前向きな意思を持っている一方、どうしようもできない諦めの気持ちをもぬぐい切れていない。 また、もしかしたらそこには、劣悪な環境だけでなく、沖縄特有の文化の影響もありそうだ。たとえば次のような記述には、その一端が表現されている。 沖縄の非行少年たちには、先輩を絶対とみなす「しーじゃー・うっとう(=先輩と後輩)」関係の文化がある。そのため、先輩から金銭を奪われ、ひどい暴行を受けても、後輩の多くはそれを大人に訴えることをしない。そして学年が変わり自分が先輩になった子は、今度は自分たちより下の後輩たちに暴力をふるう。(77ページより) ある意味では、家でも学校でも暴力を避けられないということになるのかもしれない。だとしたら、当然ながらそれは楽なことではないだろう。ましてや頼れる相手のいない女性たちの多くは、それに加えて子育ての苦労も抱えることになる。 暴力や貧困のなかで子どもを育てることは、それだけで非難の対象になってしまいがちだ。そのことは著者自身も認めているが、多くの時間を女性たちと過ごすなかで、もし同じような立場に立たされたとしたら自分も同じように振る舞うのではないかと感じた、と記している。たしかにそれは、取材者だからこそたどり着けた実感なのだろう。 だから、彼女たちの人生を「分析」するのではなく、それぞれのみてきた景色や時間に寄り添いつつ、「生活史」の形式で記すことを目指したのだそうだ。 とはいっても、その生活をもう少し引いたアングルでとらえるときに、彼女たちの拠りどころが子どもしかないこと、回帰する場所が家族しかないこと、こんなにもいくつもの困難をひとりで引き受けるしかなかったことを私はよしとしてるのではありません。それが示していることは、少ない資源で選ぶ道がそこにしかない、という事実であり、長いあいだ、女性や沖縄の問題が放置されている、日本の現実です。(256ページより) こうした記録を目にしてしまうと、たしかにそのとおりだと実感せざるを得ない。そういう意味では、実際にある現実を浮き彫りにした記録として、(売れるとか売れないとかいうこと以前に)これは間違いなく出す必要のあった書籍だといえる。しかし、だからこそ気になった点があるのも事実だ。 まずは女性たちと著者との距離感である。先にも触れたとおり、著者はひとりひとりにきちんと寄り添い、それぞれの事情を我がことのように受け止めながら取材を行なっている。まさに理想的なスタンスであるのだが、そうであるがゆえに、時として寄り添い過ぎているように思えることもあった。 全体的に、女性側からの視点が重視されすぎているように思えるということ。「この女性は気の毒だから」と、一緒に身を寄せ合って周囲に目を配っているような印象が強く、取材者としてのスタンスがやや希薄であるように思えたのだ。 寄り添いつつ、適所であえて相応の距離を保つことができていたなら、リアリティはさらに立体的になったかもしれない。 そしてもうひとつ。これはデリケートな問題だから表現するのが難しい部分もあるのだが、「なぜ沖縄なのか?」をもう少し掘り下げてほしいという思いも残った。 間違いなく、劣悪な環境から逃れて風俗の世界に足を踏み入れた彼女たちの半生は、それだけで訴えかけるものがある。しかし、各人の足跡を奥深く掘り下げているにもかかわらず、その原点であるはずの「沖縄だから、こうなったのだ」というようなバックグラウンドについての記述が少ないのだ。 本土に生まれ、本土で育ってきた人間として、皮膚感覚として受け止める機会の少ないその部分についてはもっと知りたかった。沖縄の人にしか表現できない知見がほしかったのである。 (Newsweekjapan)この記事の筆者も「なぜ沖縄なのか?」と疑問を抱いているが、読んでみて同じ感想を持った。 沖縄だけでなく、日本中どこでも同じような劣悪な環境で育ち、風俗に身を落とした少女はいる。 しかし、『裸足で逃げる――沖縄の夜の街の少女たち』という本のタイトルを見ると、沖縄だけ何か特別な事情があるような含みを感じさせるが、あえてそうしているのだろうか、という疑問が湧く。 沖縄特有の問題というと、誰もが連想するのが基地のことだろう。 しかし、複雑な環境で育った少女が風俗嬢になるのに、基地問題は関係ない。だから、なぜ沖縄なのかという疑問はやっぱり残る。 本の著者が琉球大学教育学部研究科教授で沖縄出身だから沖縄の少女たちを取材したということかもしれないが、沖縄に限ったことではないのに、まるで沖縄特有の問題であるかのような書き方には違和感を覚える。 それは、この本を手に取った人が、勝手に基地問題と関連づけて興味を持つことを意図しているように思えるからだ。 いわば、「売らんかな」でこういうタイトルにしたのではないか、ということだ。 「そんなつもりはない」と、筆者は言うだろう。しかし、それならば「李下に冠を正さず」だ。下手に勘繰られるようなことは、最初からしないほうがいい。 この記事の筆者が言っている、「女性側からの視点が重視されすぎているように思える」という部分も気になるところだ。 インタビューを受ける少女たちは、インタビュアーが求めていることを敏感に察知する。 だから、インタビュアーが聞きたそうな話をしてあげようとする。たとえば、自分の生い立ちを多少大げさに語ってみる。すると喜んでくれるから、さらにその方向の話ばかりをする。 これは、この本のインタビューに限ったことではない。 あらゆるインタビューが、こういった種類の危険をはらんでいる。 つまり、インタビュアーの無意識の誘導とインタビューを受ける側の「忖度」によって、話の内容がデフォルメされていく。だから、インタビュアーは常に軌道修正しながら、話を聞かなければならない。 少女たちの不幸な生い立ちについては同情すべき点が多いのも事実だが、本人しだいで何とかなったケースも少なからずある。だから、それを一緒くたにしてはいけないのだが、その切り分けがきっちりなされているのか。 貴重なインタビュー記録だから本にして出す価値は十分にあるが、それだけにとどまらず、不幸な状況にある少女たちを救う手立てを講じることができればベストである。というか、そこまでしなければ、この本を出す意味がない。この本の作者の次なる行動に期待したい。